MAGAZINE マガジン
【緑の地平vol.46】 三橋規宏 千葉商科大学名誉教授
会社名や組織名・役職・内容につきましては、取材当時のものです。
今こそメンツ捨て脱原発へ大転換を
(企業家倶楽部2019年4月号掲載)
日立、英国での原発建設計画を凍結
日立製作所は1月17日、英国での原子力発電所の新設事業を凍結し、2019年3月期に約3000億円の損失を計上すると発表した。約3兆円の事業費を巡る日英の政府や企業との交渉が難航して現時点での事業継続は難しいと判断したためだ。同社が断念すれば、日本企業による海外での原発事業は事実上ゼロとなり、安倍晋三政権が成長戦略の重要な柱のひとつに掲げた原発輸出は頓挫することになる。原発輸出が非現実的であることは、この数年本欄でも繰り返し指摘してきた。東京電力の福島原発事故以降、各国政府は原発の安全基準を強化したため、建設工事費は事故以前と比べ2倍以上に跳ね上がっている。原発推進派の米国でも、採算上無理があるとして、新設はほとんど進んでいない。専門家の間で「原発はもはやビジネスとして成立しない」が常識化する中で、日本は経済産業省主導で「原発輸出」を積極的に推進してきた。
だが、結果は惨憺たるものだった。経産省が今世紀初めに大きく掲げた「原子力ルネサンス」到来の旗の下で、同省の優等生だった東芝が、06年に米国の大手原子炉メーカー、WH(ウエスティングハウス)を巨額(約6600億円)で買収したが、海外での原発需要の縮小と建設費高騰で、巨額の赤字を抱え、倒産の危機に追い込まれたことはまだ記憶に新しい。
昨年12月に日本政府と三菱重工がタッグを組んで取り組んできたトルコの原発建設計画も事業費などが膨らみ過ぎて断念した。今回英国の原発建設を断念した日立はこれまでにリトアニア、ベトナムでも原発建設計画を進めてきたが、財政上の理由などで16年に中断しており、海外での事業計画はすべて失敗したことになる。
原発輸出の破綻は、日本の原発推進路線が時代の変化に遅れ、万策尽きてしまったことを示す典型例と言えるだろう。中国やロシアが採算無視で国策として推進する輸出競争に敗れたなどと無理なこじつけ理由でお茶を濁すべきではない。
事故以降国民の「原発神話」は崩壊した
福島原発事故を契機に国民の原発アレルギーはかつてなく強まっている。事故前の日本では、国民の多くが「原発神話」を信じてきた。日本の原発はかつてチェルノブイリの大惨事を引き起こしたソ連製の原発と違って、二重、三重の安全チェックをしており、事故など起こりえないという政府、電力会社の説明を多くの国民は疑わなかった。ところが深刻な福島原発事故を経験することによって、今や国民は「100%安全な原発など存在しないこと」を学んだ。深刻な放射能汚染で16万人を超える人々が避難民として住処を追われ、いまだに多くの人々が帰還できない状態が続いている。
しかも近い将来、日本列島で大地震が発生する可能性が高いと多くの地震学者が警告している。特に危険が指摘されているのが南海トラフ大地震の発生だ。南海トラフとは静岡県沖から四国、九州の沖合まで続く海底のくぼ地で、約100年から200年おきに大地震が繰り返し起こっている。過去の経験則から見ると、50年頃までに起こる可能性は極めて高いと予想されている。内閣府の試算によると、南海トラフ大地震が起これば、最大32万3000人が死亡し、経済被害は215兆円に及ぶと推計している。大地震が発生する前に大事故につながりかねない原発を廃止することは、国民の安全対策として政府の最優先課題であるはずだ。
次々と破綻政府の原発推進計画
しかし政府を主導する経産省、電力会社、原子炉メーカーなど原発で利益を享受してきた既得権益グループは、国民の反原発意識の高まりを無視し、原発事故後も事故前と同様、原発推進の旗を高く掲げ続けている。その岩盤のような結束の強さに改めて驚く。
昨年7月初めに閣議決定した新エネルギー基本計画でも30年度の全電源に占める原発比率を20~22%にする目標を掲げている。そのためには既存の原発を30基程度稼働させなければならないが、現在は9基を稼働させたに過ぎない。地域住民の反対を押し切って30基稼働させることは簡単にはできそうにない。まして新増設などは不可能だろう。
経団連の中西宏明会長(日立会長)は最近の記者会見で原発の再稼働が進まない状況について、「私はどんどん進めるべきだと思っている。原子力というエネルギーを人類のために使うべきだ」との見解を述べている。海外がダメなら、再び国内の原発再稼働、新増設に踏み込むべきだとの姿勢がにじみ出ている。
世耕弘成経済産業相は日立凍結について質問されると、「原発を今後利用したいと思っている国がマジョリティ(多数派)。日本の技術が世界に貢献できる可能性はある」と原発輸出になお意欲的発言をしている。
現実と遊離した政府の原発推進政策は次々と破綻し、巨額の税金が失われている。
たとえば、通産省が16年末に試算した福島原発事故の処理費は21・5兆円に達する。3年前の13年の想定金額(約11兆円)の約2倍に膨らんだ。この内、除染費4兆円、放射性物質を保管する中間貯蔵施設の建設・管理費1.6兆円は税金などの国費で賄う。廃炉・汚染水対策(8兆円)、賠償(7.9兆円)は東電が負担するが、これらの費用は最終的には電気料金の形で消費者に転嫁されることになる。
青森県・六ヶ所村の核燃料サイクルのための再処理工場も2兆円超の巨費が投じられながら20年以上も稼働しない状態が続いている。1兆円以上の国費をつぎ込んできた高速増殖原型炉「もんじゅ」の解体は、これから30年の歳月をかけて廃炉作業が続けられる。その費用として3750億円の国費が投じられる。専門家の間では実際にはその倍以上の費用がかかると指摘されている。増え続ける高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場も適地が見つからない状態だ。適地が見つかったとしても、その安全処理のための費用はかなりの金額になると見られている。いまや原発推進は金食い虫なのである。これらのお金が再生可能エネルギーの開発に振り向けられていればかなりの成果が期待できたはずだと思わずにはいられない。
原発推進路線の大転換は時代の要請
原発は順調に稼働している場合は、これほど便利なエネルギーはないと思われるが、一度事故を起こすとその費用は計り知れない程大きく膨らむ。また、廃炉のために長い歳月と費用がかさむ。
原発推進にからむ様々な計画がこの数年の間に次々と破綻し、原発事業の推進がむずかしくなった。政府の原発政策が「絵に描いた餅」に過ぎなかったことを物語っている。
この際、政府はメンツにこだわらず、時代に合わなくなった既存の原発推進路線を大転換させ、国民の安全を最優先し、脱原発、再生可能エネルギー中心の新たなエネルギー政策を作成し、実施していく決断をすべきだろう。
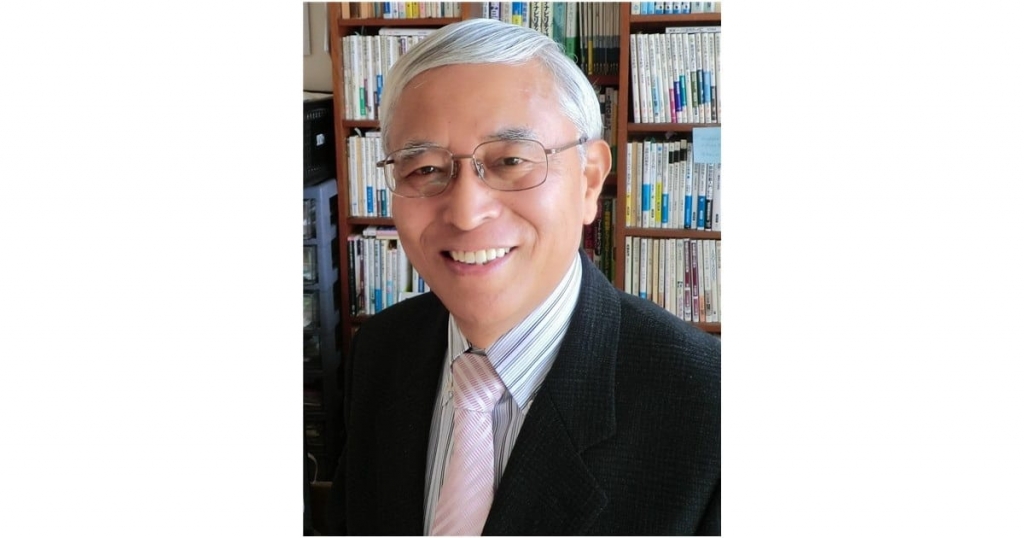
プロフィール
三橋規宏 (みつはし ただひろ)
経済・環境ジャーナリスト、千葉商科大学名誉教授。1964 年慶応義塾大学経済学部卒業、日本経済新聞社入社。ロンドン支局長、日経ビジネス編集長、論説副主幹などを経て、2000年4月千葉商科大学政策情報学部教授。2010 年4月から同大学大学院客員教授。名誉教授。専門は環境経済学、環境経営論。主な著書に「ローカーボングロウス」(編著、海象社)、「ゼミナール日本経済入門25 版」(日本経済新聞出版社)、「グリーン・リカバリー」(同)、「サステナビリティ経営」(講談社)、「環境再生と日本経済」(岩波新書)、「環境経済入門第4 版」(日経文庫)など多数。中央環境審議会臨時委員、環境を考える経済人の会21(B-LIFE21)事務局長など兼任。
